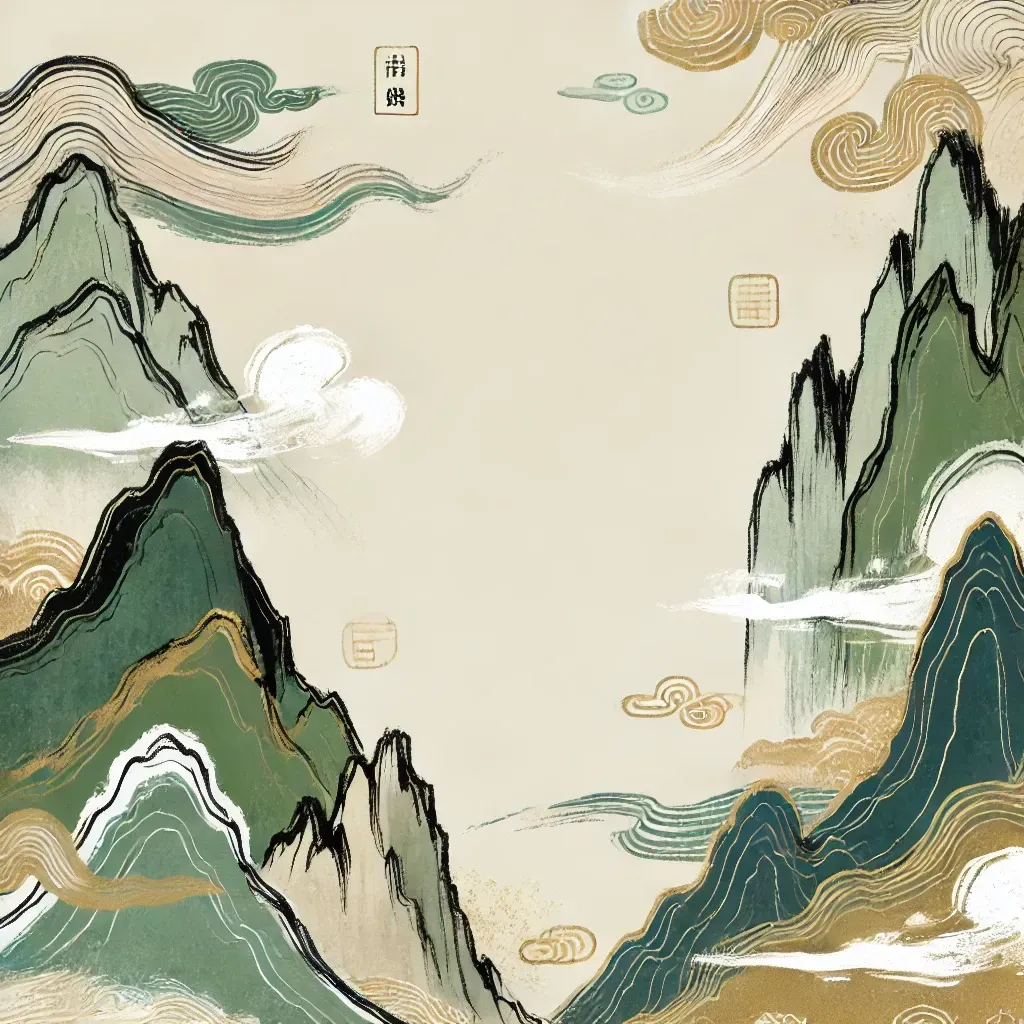1980年代の台湾で、老人茶館に足を踏み入れると、十中八九特殊な「火の香り」に出会った。それが香港「堯陽鉄観音茶王」の象徴的な香気だった——重火炭焙、茶湯は厚重、滋味は濃厚。四両(約150グラム)一缶で七百元、当時としてはすでに高価な茶だったが、それでも供給が需要に追いつかなかった。両岸が開放されていなかった時代、香港から来たこの茶缶は、台湾で重い口当たりの茶韻を好む人々の最愛となり、一世代の茶通の記憶に深く刻まれた炭焙の味となった。
四両七百元の天下無双
「堯陽茶行」が香港で発売した四両鉄缶入り「鉄観音茶王」は、台湾で大いに歓迎された。この現象の背後には、特殊な時代背景があった。両岸が開放されていなかった時代、台湾の消費者は安渓鉄観音に直接触れることができず、香港や東南アジアなどの茶行を通じて間接的に購入するしかなかった。「堯陽茶王」はちょうどこの市場の空白を埋めた。
四両で七百元、80年代としてはかなり高い価格だった。当時の台湾高山茶でも一斤数百元程度だったことを考えれば。しかし「堯陽茶王」の位置づけは異なっていた——ターゲットは茶を理解し、「観韻」を飲み分けられる茶通である。これらの人々は価格を気にせず、本物の安渓鉄観音の韻味を求めていた。
市場の反応がこの戦略の成功を証明した。80年代後半には、一斤「堯陽茶王」はすでに三千元近くまで値上がりし、この価格は当時台湾で興った品評会茶の価格と対抗できるものだった。台湾市場で足場を固め、地元茶と競争できたことは、「堯陽茶王」の品質と評判を物語っている。
炭焙火香の独特な魅力
「堯陽茶王」の最大の特色は、あの明らかな「炭焙」の香りだった。80年代、鹿港の品茗愛好家が来客をもてなす際、事前に茶名を告げず、ただこの茶は「天下無双」だと言い、茶湯の滋味に「炭焙」の味があると謳った。この茶に精通した人は、茶湯を一口含むや否や、即座に「茶王」の名を叫んだ。茶友は答えた。「お目が高い」と。
この小さなエピソードは、「堯陽茶王」の識別度の高さを物語る。あの独特な火の香りは、一度飲めば忘れられない。これは淡い焙煎香ではなく、厚重で、安定し、覇道的な炭火の気配で、まるで味蕾を通じて炭火の温度を感じられるかのようだった。
炭焙は伝統的な焙煎方式である。木炭を熱源とし、温度が安定し、熱力が柔和だが、最も重要なのは茶葉に特殊な「火香」を与えられることだ。この香気は、電熱乾燥機では複製できない。「堯陽茶王」はまさにこの伝統工芸を利用して、唯一無二の風味特色を打ち出した。
しかし、重火炭焙は諸刃の剣でもあった。支持者は、炭焙が茶葉の青臭さを除去し、厚みと層次を増し、茶湯をより醇厚で甘美にすると考えた。批評者は、過度な火の香りが茶葉本来の清香や花果香を覆い隠し、烏龍茶が持つべき高揚した香気を失わせると考えた。
「大陸茶」焙火が重いという印象
「堯陽茶王」の知名度が高かったため、その「炭焙」スタイルは台湾消費者の心に深い印象を残した。これが台湾消費者が「大陸茶」は焙火が重く、香りに欠けるという印象を持つ理由でもあった。
この印象は完全に正確とは言えない。実際、安渓鉄観音の製造スタイルは多様で、重火の伝統型もあれば、清香の現代型もある。「堯陽茶王」が代表するのは伝統的な重火路線で、強調するのは「韻」であって「香」ではない。しかしその台湾市場での影響力があまりに大きかったため、多くの人がすべての安渓茶がこのスタイルだと誤解してしまった。
この誤解は、両岸開放後に徐々に解消された。台湾消費者がより多様な安渓鉄観音に触れる機会を得たとき、安渓茶にも清香型、花香型、果香型など異なるスタイルがあることを初めて知った。しかし80年代の茶通にとって、「堯陽茶王」の炭焙の味は、すでに記憶に深く刻まれ、「正統鉄観音」の基準となっていた。
緑観音:手頃な代替選択
高価な「茶王」以外に、堯陽茶行が市場で販売していた「緑観音」は、おおむね「本山種」を主とし、価格は三分の一安く、台湾の老人茶館で流行した。
「緑観音」の位置づけは明確だった——予算が限られているが、それでも安渓茶の韻を味わいたい消費者向けである。純種の紅芽鉄観音ではないが、本山種から製成された茶葉は「香気甚高,其味有如鉄観音」であり、一般消費者には十分満足できるものだった。
価格が三分の一安いということは、四両の「緑観音」はおよそ二百数十元で、この価格帯により多くの人が安渓茶に触れる機会を得た。老人茶館では、「緑観音」が日常飲用の選択となった。茶客たちが集まり、一壺の茶を淹れ、碁を打ち、おしゃべりをし、時間を過ごす。「緑観音」は無数の悠々とした午後に寄り添った。
この高低組み合わせの製品戦略は極めて賢明だった。「茶王」がブランドイメージを確立し、ハイエンド顧客を引きつける。「緑観音」が市場カバレッジを拡大し、潜在的消費者を育成する。両者が相互補完し、堯陽茶行が台湾市場で足場を固めることを可能にした。
海外市場の活況と故郷の波乱
「堯陽茶王」の台湾、香港などの海外市場での成功は、鉄観音の人気の高さを反映していた。堯陽茶王は品質を重視し、海外市場は極めて活況を呈した。しかし、安渓本地の鉄観音茶市は、大環境の影響を受けて浮き沈みし、何度も波乱を経験した。
『安渓茶葉史話』には次のように記されている。輸出市場が十分に大きくなく、販売が不振で、安渓烏龍茶は次第に下り坂となった。民国二十三年(1934年)、全県の茶葉総生産量は底に達し、440トンに満たなかった。民国二十六年、日中戦争勃発後、茶政は乱れ、官吏は私利を図り、加えて烏龍茶の主要輸送港である廈門、汕頭が相次いで陥落し、生産は絶滅の危機に瀕した。
1949年までに、全県の茶園は20920ムーに減少し、茶葉生産量は419.6トンに下がった。当時こんな民謡が流行った。「金枝玉葉何足惜,観音不如菜豆葉;茶葉上市没人叫,砍下茶樹当柴焼」かつて貴重だった鉄観音が、野菜を植えるより実際的でないとは——この悲しい民謡は、茶農家の絶望を物語っている。
この故郷と海外市場の落差は、強烈な対比を形成した。堯陽茶王が台湾で一斤三千元で売れていたとき、安渓の茶農家は茶樹を切って薪にしていた。これは海外茶商の重要性を示している——これらの「海外先鋭部隊」が継続的に買い付け、普及させなければ、安渓鉄観音はとうに歴史の流れの中で消えていたかもしれない。
一世代の炭焙記憶
台湾の茶通にとって、「堯陽茶王」は単なる一缶の茶ではなく、一つの時代の記憶である。両岸が隔絶されていたあの時代、香港から来たこの茶は、故郷への想像、本物の味への追求を担っていた。
80年代の老人茶館は、炭焙の香りに満ちていた。茶客たちが円座して、茶を淹れ、味わい、論じる。「堯陽茶王」の茶湯が杯に注がれると、あの厚重な火の香りが鼻を衝き、皆が会心の笑みを浮かべる——これこそが「本物の」鉄観音なのだと。
今や両岸はとうに開放され、台湾消費者は様々なスタイルの安渓鉄観音を直接購入できる。市場の嗜好も変化し、清香型、花香型が次第に主流となり、重火炭焙はかえってニッチな選択となった。しかし80年代を経験した茶通にとって、「堯陽茶王」の炭焙記憶は、永遠に代替できないものなのだ。
次に茶通の年配者に出会ったら、聞いてみてはどうだろう。「堯陽茶王を覚えていますか?」おそらく、懐かしそうな笑顔を浮かべ、あの炭焙の黄金時代について語り始めるだろう。