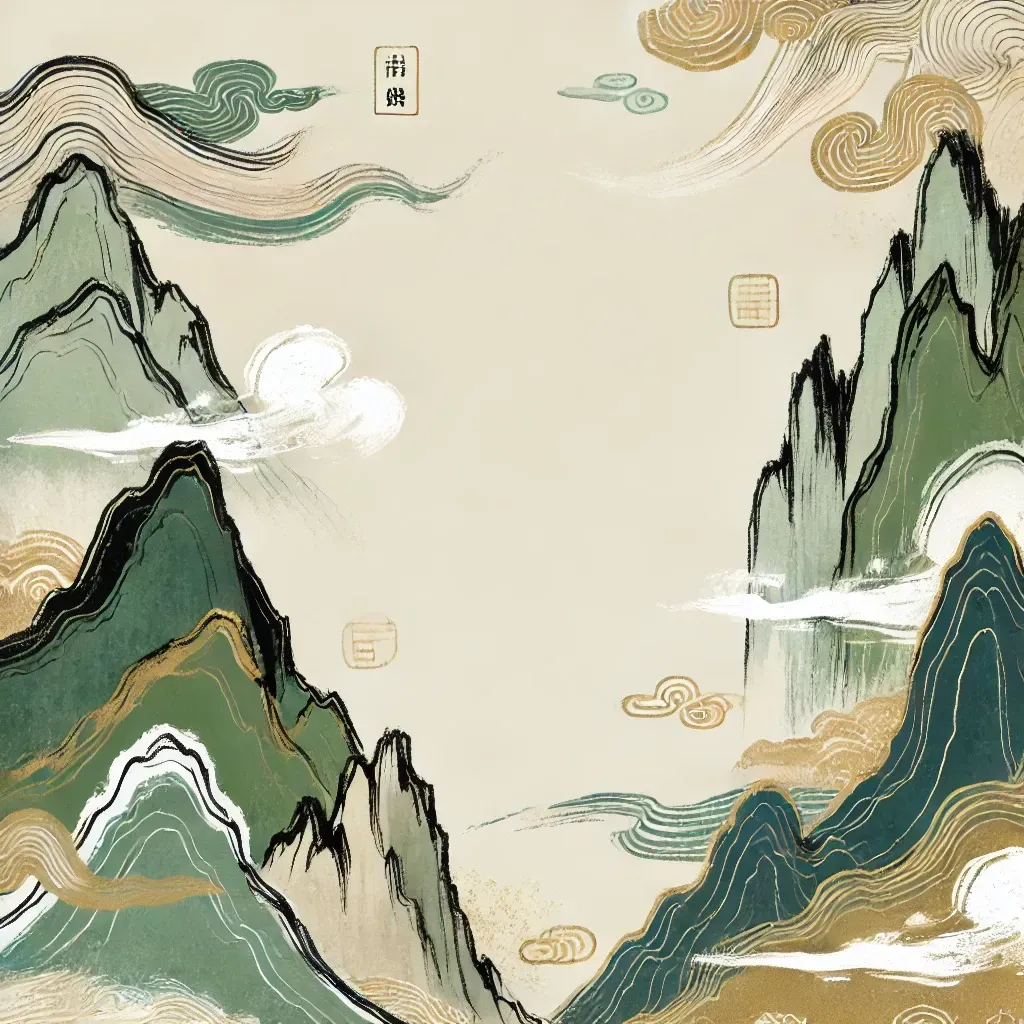「金枝玉葉何足惜,観音不如菜豆葉;茶葉上市没人叫,砍下茶樹当柴焼」——この1940年代に安渓茶区で流行った民謡は,茶農家の絶望と哀愁を余すところなく語っている。かつて「金枝玉葉」のように貴重だった鉄観音が,抗日戦争の戦火の中で,野菜を植えるより実際的でなくなってしまった。1934年に生産量が底を打ち,1949年に茶園面積が二万ムーまで激減するまで,安渓鉄観音は前代未聞の大災厄を経験した。これは単なる数字の下落ではなく,一つの茶業王国の崩壊である。
1934年:底を打った440トン
安渓鉄観音の危機は,抗戦勃発前にすでに浮上していた。『安渓茶葉史話』には次のように記されている。輸出市場が十分に大きくなく,販売が不振で,安渓烏龍茶は次第に下り坂となった。民国二十三年(1934年),全県の茶葉総生産量は底に達し,440トンに満たなかった。
この数字はどれほど驚くべきものか?全盛期の安渓では,茶葉の年間生産量は数千トンに達していた。それが今や440トンまで急落したということは,生産量が八割以上減少したことを意味する。これは単純な市場変動ではなく,産業全体の崩壊である。
なぜこのような状況が生まれたのか?根本原因は市場需要の萎縮にある。二十世紀初頭,安渓と中国大陸は高級安渓茶を消費できず,産地で安住することは難しかった。海外市場は存在したものの,交通,政局,競争などの要因に制限され,「輸出市場が十分に大きくなく」,安渓の大量の茶葉産出を吸収できなかった。
供給過剰の局面により,茶価は暴落した。茶農家が一年苦労して作った茶葉を市場に持っていっても「誰も声をかけない」——買い手がつかない。売れない茶葉は倉庫で腐り,茶農家は元手を失った。茶を植えるより野菜を植える方がまし,少なくとも野菜なら自分で食べられ,元手を完全に失うことはない。
1937年:戦争の致命的一撃
1934年が経済危機だったとすれば,1937年の抗日戦争勃発は,ラクダの背を折る最後の一本の藁だった。
民国二十六年(1937年),抗日戦争が全面的に勃発した。『安渓県志』には次のように記されている。「抗日戦争勃発後,茶政は乱れ,官吏は私利を図り,加えて烏龍茶の主要輸送港である廈門,汕頭が相次いで陥落し,生産は絶滅の危機に瀕した」
この一文は三つの致命的要因を語っている。第一に,茶政の混乱。戦時政府は茶業管理に手が回らず,もともとの生産販売秩序が完全に崩壊した。第二に,官吏の私利追求。乱世の中,一部の官吏が機に乗じて懐を肥やし,名目を立てて茶農家に課税し,茶農家の負担は雪だるま式に増えた。第三に,そして最も致命的なのは——廈門,汕頭の相次ぐ陥落である。
廈門と汕頭は,安渓烏龍茶の最も主要な輸送港だった。海外へ輸出するすべての茶葉は,この二つの港を経由して運び出される必要があった。この二つの港が陥落すると,海上貿易ルートが遮断され,安渓茶葉は香港,シンガポール,タイなどの海外市場へ運べなくなった。
海外市場を失うことは,主要収入源を失うことを意味した。海外茶商は仕入れに来られず,堯陽の王氏一族,南洋に開設された百軒の茶行,故郷とのつながりが戦火によって断たれた。安渓茶業は,真の絶境に陥った。
1949年:わずか419.6トンの悲哀
戦争の摧残により,安渓茶業は一敗地にまみれた。1937年から1949年まで,まる十二年の戦乱で,茶園は大量に荒廃し,茶樹は管理されず,茶農家は次々と転業した。
『安渓県志』は心痛むデータを記録している。1949年までに,全県の茶園はわずか20920ムーとなり,茶葉生産量は419.6トンに下がった。
20920ムーの茶園は,安渓という「福建省最大の茶産地」にとって,悲しむべき数字である。生産量419.6トンは,1934年の440トンよりもさらに低い。十五年間,安渓茶業は回復しなかっただけでなく,さらに下降し続けた。
この数字の背後には,無数の茶農家の血と涙がある。自家の鉄観音茶樹を切り倒してサツマイモや菜豆に植え替えた者,茶園を放棄して出稼ぎに出た者,荒れ果てた茶園を守り,絶望の中で転機を待った者。
民謡に込められた絶望:茶樹を薪にする
「金枝玉葉何足惜,観音不如菜豆葉;茶葉上市没人叫,砍下茶樹当柴焼」
この民謡は,茶農家の心の声の真実の描写である。一句一句が,絶望と無力感に満ちている。
「金枝玉葉何足惜」——鉄観音はかつて宝として,「金枝玉葉」のように貴重視されていた。しかし今,これらの貴重な茶樹に何を惜しむ価値があろうか?植えても売れず,徒に人力物力を浪費するだけだ。
「観音不如菜豆葉」——最も心が痛む一句である。鉄観音を植えるより,菜豆(インゲン豆)を植える方がまし。菜豆なら少なくとも自分で食べられ,金に換えられる。鉄観音は倉庫で腐るだけ。茶農家の価値判断は,品質追求から生存追求へと転換した。
「茶葉上市没人叫」——市場に持っていっても,誰も値をつけず,誰も買わない。茶農家は一年の苦労の成果が誰にも顧みられないのを目の当たりにし,その無力感と挫折感は言葉に尽くしがたい。
「砍下茶樹当柴焼」——最も絶望的な選択である。茶葉が売れないなら,茶樹を切り倒して薪にしてしまえ。少なくとも飯を炊き暖を取ることはでき,完全な無駄にはならない。この一句は,茶農家が茶業を徹底的に放棄したことを象徴している。
海外先鋭部隊の無力
皮肉なことに,安渓茶業が絶境に陥っていたまさにそのとき,海外市場では鉄観音への需要が依然として存在していた。シンガポール,タイ,ミャンマーの華人茶商は,依然として安渓の茶葉を待っていた。しかし戦争がサプライチェーンを断ち切り,買いたくても買えなかった。
『安渓茶葉概説』にはかつてこう記されていた。安渓茶葉は「毎年国のために外貨四十万から八十万元を稼ぎ⋯⋯安渓は毎年約三ヶ月の食糧不足があり,隣県や輸入品から米麺を購入するのは華僑送金と茶葉収入で赤字を補填し,農村経済が崩壊しないようにするためであった」
この一節は海外市場が安渓経済に占める重要性を説明している。しかし戦争が貿易を遮断し,華僑送金も茶葉収入も途絶えると,農村経済は本当に崩壊した。かつて故郷を支えた「海外先鋭部隊」も,戦火の前では無力だった。
大災厄の後:困難な再生
1949年以降,安渓茶業はゆっくりと回復し始めた。1952年,安渓茶廠は大規模な機械化生産を採用し,効率を高めた。改革開放後,海外市場が再び開かれ,鉄観音は徐々に元気を回復した。
しかしあの「観音は菜豆葉に及ばず」の歳月は,永遠に安渓人の集団記憶に残った。それは後世に警告する。一つの産業の興亡は,品質や技術だけで決まるのではなく,大環境,政局,市場に制約される。どれほど良い茶葉も,戦乱の中では薪に過ぎない。
今日,鉄観音を一杯味わうとき,絶境の中で踏ん張った茶農家たちを思い起こしてはどうだろう。彼らがすべての茶樹を切り倒さず,完全に諦めなかったからこそ,鉄観音の火種が保存され,平和の時代に再び花開くことができたのだ。
「観音は菜豆葉に及ばず」の時代はすでに過ぎ去ったが,この民謡は私たちに思い起こさせる。平和を大切にし,苦労して得られた一杯一杯の茶を大切にしようと。